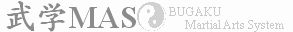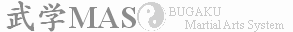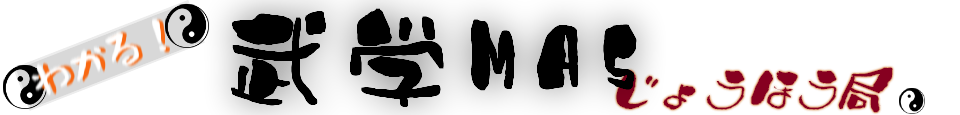基礎功夫
続、騎馬式(馬歩)の取り方・作り方
腰の落としは「正三角」が基準
前回「騎馬式(馬歩)の取り方・作り方」からの続きです(^-^)/
前回は騎馬式(馬歩)を取る時の腰の落とし方についての注意点などを書きました。
今回は、その注意点を踏まえたうえで
腰を落とす高さの基準と膝への注意点を中心に書いてみたいと思っています。
まず、腰を落とす高さは
練功(練習)の目的によっていろいろとあるのですが
武学MASでは
Ⓐ尾閭
Ⓑ膝頭
Ⓒ踵
の三点が横から見たときに「正三角形」になる高さを基準とします。
(写真参照)
この「正三角形」は杓子定規で測ったようなきちんとしたものではなく
あくまでも比喩としてです。
比喩ではありますが
余りにも遠いのも考えものです(( ̄_ ̄ )
自分の身体感覚上での
「正三角形」までの高さを身につけることが大切です。
この三角形から
当会では騎馬式を取るときに「三角馬歩」(愛称)と言ったりします( ̄ー ̄)
当会では騎馬式を取るときに「三角馬歩」(愛称)と言ったりします( ̄ー ̄)
写真からもわかりますがこの「三角馬歩」、膝がつま先より前に出てしまいますので
一般的には膝を痛めやすい形となります。
一般的には膝を痛めやすい形となります。
しかし、正しい姿勢と身体操作法(骨盤と股関節の動作的分離)が身について来れば
膝への負担はほぼなくなります。
これは企業秘密にでもしておきたいのですが、当会の「三角馬歩」の練習することで
「骨盤と股関節の動作的分離を身につける」ことができるようになりますd(。ゝд・)
ついで
腰を落とした時の正面から見た膝頭の位置ですが
開き過ぎず

閉じ過ぎず

腰を落とす前の位置から素直に前に出した位置ぐらいとなります

この時、外からは見えにくいですが
大腿部から膝頭までの内部において
股関節は外旋し、膝はその外旋力に負けて開いてしまわないように内に絞める 。
このような力がはたらいています(・0・。
こうすることで膝はその位置にあるだけではなく
「外から押されても強く、内から押されても強い」
状態となります。
外から一見するとわからないのですが触れてみると力強さが伝わります。
上記のように武学MASではただ形を取るだけではなく、
その内に働く力も重要なこととして学習していきます。
今回は「歩形」としての騎馬式(馬歩)を紹介しました。
最後に少し触れました、外から一見しただけでは分かりにくい内部の感覚を重視するような騎馬式の練習を
「騎馬式站樁功」と言います。
武学MASの「騎馬式站樁功」には
身体各部に対する要求
力の加え方、
意識の取り方、
呼吸など
書くのが面倒になるほど多くの
いわゆる秘訣(笑、 がございます。
外見(外形)だけではなく、上記のような内面(内意)にも興味がございましたら
お気軽にお問合わせ いただき是非レッスンを受講してみてください(。>ω<。)ノ
ついで
腰を落とした時の正面から見た膝頭の位置ですが
開き過ぎず

閉じ過ぎず

腰を落とす前の位置から素直に前に出した位置ぐらいとなります

この時、外からは見えにくいですが
大腿部から膝頭までの内部において
股関節は外旋し、膝はその外旋力に負けて開いてしまわないように内に絞める 。
このような力がはたらいています(・0・。
こうすることで膝はその位置にあるだけではなく
「外から押されても強く、内から押されても強い」
状態となります。
外から一見するとわからないのですが触れてみると力強さが伝わります。
上記のように武学MASではただ形を取るだけではなく、
その内に働く力も重要なこととして学習していきます。
今回は「歩形」としての騎馬式(馬歩)を紹介しました。
最後に少し触れました、外から一見しただけでは分かりにくい内部の感覚を重視するような騎馬式の練習を
「騎馬式站樁功」と言います。
武学MASの「騎馬式站樁功」には
身体各部に対する要求
力の加え方、
意識の取り方、
呼吸など
書くのが面倒になるほど多くの
いわゆる秘訣(笑、 がございます。
外見(外形)だけではなく、上記のような内面(内意)にも興味がございましたら
お気軽にお問合わせ いただき是非レッスンを受講してみてください(。>ω<。)ノ
注意):
このハウツーブログは基本的に武学MASで学ばれた方の予習、復習用、
武学MASの技術紹介用、参考資料用として記事を構成しています。
独習独学を薦めるものではありません。
このハウツーブログは基本的に武学MASで学ばれた方の予習、復習用、
武学MASの技術紹介用、参考資料用として記事を構成しています。
独習独学を薦めるものではありません。
独学での怪我やそれに関するトラブルに関しましては当方では
責任を負えません。
独学でこの記事を読み練習される場合は 自己責任でお願いします。
独学でこの記事を読み練習される場合は 自己責任でお願いします。
できればレッスンを受けていただき正しい知識と身体認知をもって練習していただければうれしいです。
2017/04/07